皆さんこんにちは、たたらです。
今回は『腕立て伏せの基本から徹底解説!正しい方法を学ぼう!【後編】』ということで前回の続きを話していこうと思います。
効果を高めるトレーニングテクニック
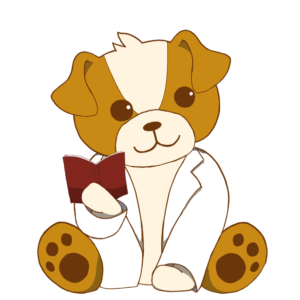 たたら
たたら
バリエーションの導入
腕立て伏せのバリエーションを取り入れることで、異なる筋肉を刺激し、トレーニングの効果をより高くできます。
1.ワイドプッシュアップ
手を広く開き、胸を強調します。広い手の位置により、大胸筋などの筋肉が重点的に使われます。
2.ナロープッシュアップ
手を身体に寄せ、上腕三頭筋に焦点を当てます。肩幅よりも手を狭めることで、上腕三頭筋への負荷が増します。
3.ダイヤモンドプッシュアップ
手をくっつけてダイヤモンド形に配置し、上腕三頭筋と大胸筋を同時に刺激します。この形態は、特に上腕三頭筋の強化に有効です。
インターバルトレーニングの利用
1.タイマーの活用
腕立て伏せと休息のインターバルを決め、効果的なサーキットを作成しましょう。例えば、30秒の腕立て伏せ、30秒の休息を繰り返すサイクルなどです。自分の身体と相談しながら時間を延ばしていきましょう。
2.ハイインテンシティインターバルトレーニング(HIIT)
短い間隔で高強度の腕立て伏せを行い休息することを繰り返すことで、心肺機能と筋力を同時に向上させます。
ウェイトを使った腕立て伏せの方法
1.重りを使用
手首に軽量の重りをつけるか、背中に重りを載せて行うことで、上半身の筋肉に追加の負荷をかけます。※まずは重りなしからスタートすることを推奨します。
2.バーベルプッシュアップ
バーベルを使用して、地面に対して水平に腕立て伏せを行います。これにより、安定性を必要とするため、全身の筋肉がより強く刺激されます。
これらのトレーニングテクニックを組み合わせることで、単調さを排除し、効果的かつ総合的な腕立て伏せのトレーニングが可能です。進行レベルに応じてバリエーションを取り入れ、自身に合った負荷を見つけることが重要です。
よくある間違いと修正方法
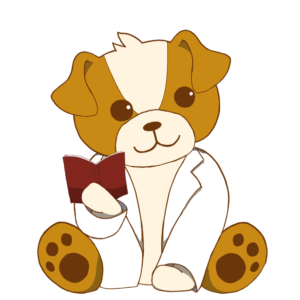 たたら
たたら
腕立て伏せ中のよくある間違い
1.肘を真横に広げる
肘を真横に広げると、肩への負担が増え、怪我のリスクが高まります。前編でも話した通り約45°に脇を開いて行いましょう。
2.お尻を上げすぎる
お尻を上げると腰への負担が減ると言われていますが、実は背中から腰にかけて余分な負荷がかかり、大胸筋胸や上腕三頭筋への刺激が減少します。お尻を上げる形で行う際は少しだけにして、極力体をまっすぐ保つように注意しましょう。
3.顔を前に向ける
顔を前に向けて頭を突き出すと、首に不必要なストレスがかかります。頭までまっすぐ保ち、身体と一直線に保つようにしましょう。
フォームの崩れを防ぐためのヒント
1.鏡やビデオを利用する
鏡やビデオを使って自分のフォームを確認することで、間違いや崩れを早期に発見しやすくなります。
2.体幹を意識する
体幹をしっかりと使うことで、体全体の安定性が向上し、フォームの崩れを防ぎます。お腹を引き締め、意識的に体幹を使いましょう。
3.プロのアドバイスを得る
自分では良くわからない!って方は、トレーナーやフィットネスの専門家にアドバイスを求めることで、個々のフォームに合った修正ポイントを得ることができます。
これらのポイントを意識して腕立て伏せを行うことで、効果的なトレーニングが可能となり、同時に怪我の予防にも繋がります。フォームの崩れに気を付け、正確な動きを心がけましょう。
腕立て伏せの成果をモニタリングする方法
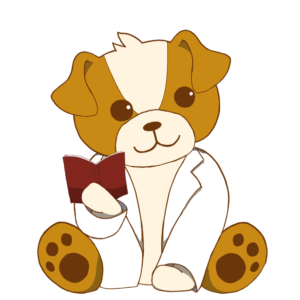 たたら
たたら
回数・頻度のモニタリング
1.トレーニング日誌の作成
腕立て伏せのセット数や回数、使用したフォーム、トレーニングの難易度などを日誌に記録しましょう。これにより、進捗や弱点を把握しやすくなります。
2.トレーニングアプリの活用
専用のトレーニングアプリを利用することで、腕立て伏せの回数やセット数を自動的に記録し、進捗をグラフで確認することができます。
3.最大挑戦回数の記録
定期的に行う最大挑戦回数のテストを通じて、腕立て伏せの最大回数を記録し、成果の向上を把握します。
腕立て伏せによる体の変化の観察方法
1.写真による比較
定期的に腕立て伏せの前後で全身の写真を撮り、体の変化を視覚的に確認します。特に胸や腕の筋肉の発達が写真で明確になります。
2.寸法の測定
腕や胸、腰などの特定の部位の寸法を測定し、トレーニング前後で変化があるかを確認します。これにより、筋肉の増減や引き締まりを数値で把握できます。
3.身体の感触の変化
トレーニングによって筋肉が発達すると、身体の感触が変わります。触ってみて柔らかさや硬さの変化を感じ、トレーニングの成果を確認します。
4.体力の向上
腕立て伏せの定期的なトレーニングにより、日常の体力が向上することを観察します。日常生活での動作や他のトレーニングにおいて感じるパフォーマンスの向上を確認します。
これらの方法を組み合わせて、腕立て伏せによる成果を継続的にモニタリングすることで、トレーニングの効果を最大化し、モチベーションを維持することが可能です。私は前後の確認を特におすすめします。意外と変化に気づくものですよ。
クールダウンとストレッチ
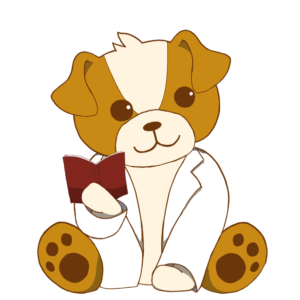 たたら
たたら
トレーニングの後に行うべきストレッチング
1.全身のストレッチング
トレーニングで使った全身の筋肉を対象にしたストレッチングを行います。大きな筋群から順に、ゆっくりとした動きで行いましょう。
2.特定部位のストレッチ
特に使った部位や気になる箇所に焦点を当てたストレッチングを追加します。例えば、腕立て伏せ後には腕や肩、背中のストレッチングが有効です。
3.スタティックストレッチ
筋肉を引き伸ばす静的ストレッチ(スタティックストレッチ)を取り入れます。各ポーズで15-30秒キープし、ゆっくりと深い呼吸を心がけます。
筋肉の回復のためのクールダウンの重要性
1.乳酸の排除
クールダウンは血流を整えることで、トレーニング中に蓄積した乳酸を効果的に排除します。これにより、筋疲労を軽減し、回復を促進します。
2.心拍数の安定化
急激な運動の終了後、急激に静止することは心臓に負担をかける可能性があります。クールダウンは徐々に心拍数を下げ、安定化させるのに役立ちます。
3.急激な血圧変動の予防
トレーニング中の急激な血圧の上昇を、クールダウンが緩和し、急激な血圧変動からくるめまいや不調を予防します。
4.筋肉と関節の柔軟性の維持
クールダウン中に行うストレッチは、筋肉と関節の柔軟性を保ち、トレーニング後の硬直感を軽減します。
5.心身のリラックス
クールダウンはリラックスの一環でもあります。適切な方法でクールダウンを行うことで、心身ともにリラックスし、トレーニングの満足感を高めます。
クールダウンとストレッチはトレーニングの締めくくりとして重要です。十分な時間をかけて行うことで、怪我の予防やトレーニング効果の最大化に寄与します。
おわりに
お疲れ様でした!
2回に渡って腕立て伏せについて語っていきましたが、意外と知らなかったこともあるんじゃないですか?
安全に効率良くトレーニングしていきましょうね!
今回もお付き合いありがとうございました!それでは!
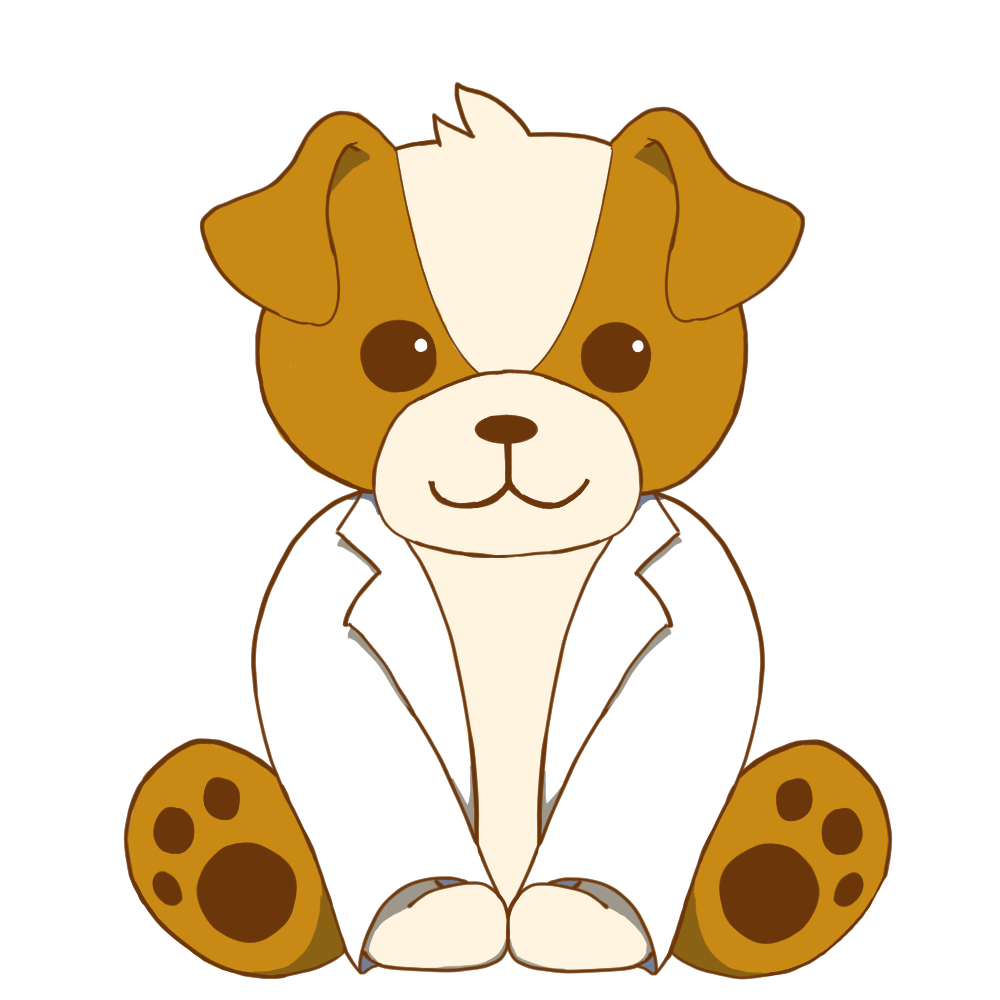 健楽ひろば
健楽ひろば 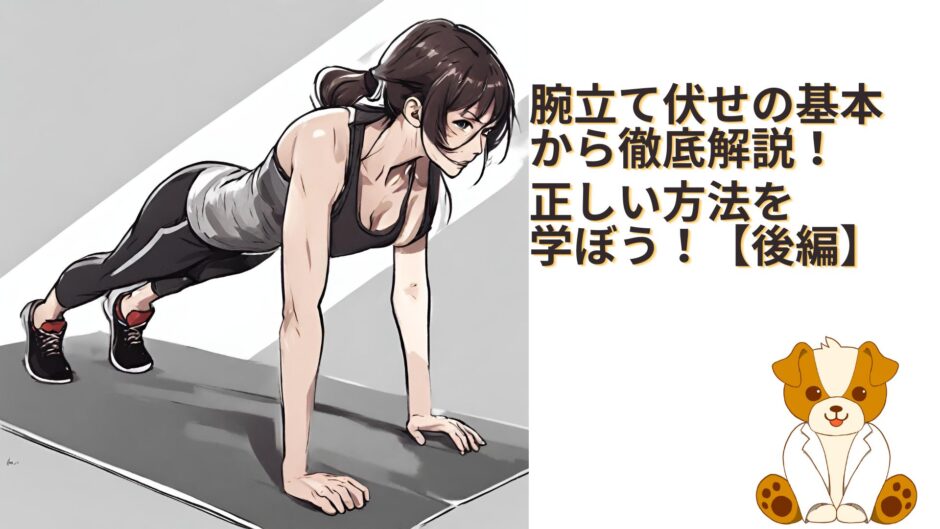



[…] 腕立て伏せの基本から徹底解説!正しいフォームを学ぼう!【後編】 […]